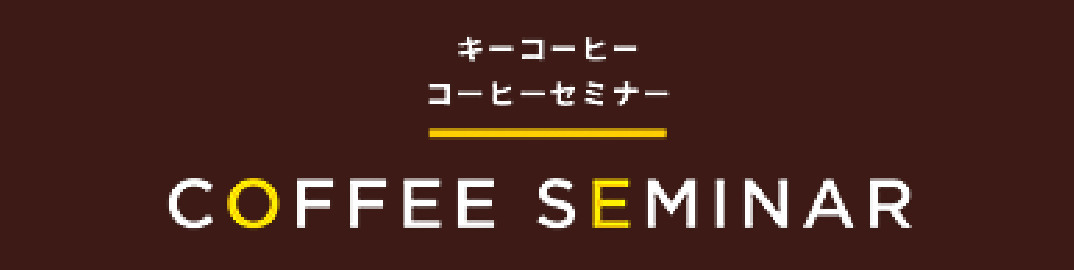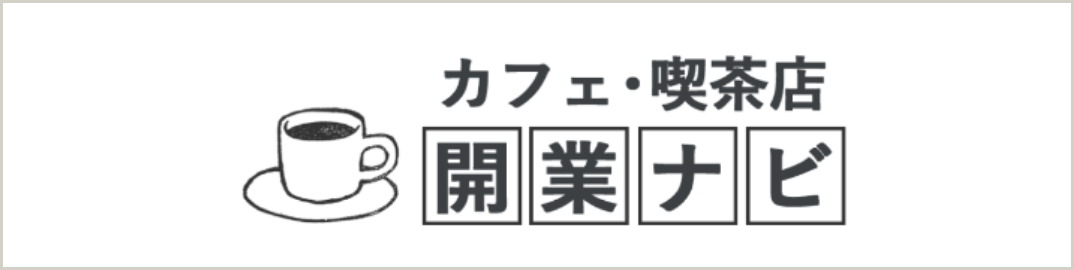コーヒーの歴史を知ろう~人との関わりや文化として根づくまでを紹介
2025.11.04
豆知識
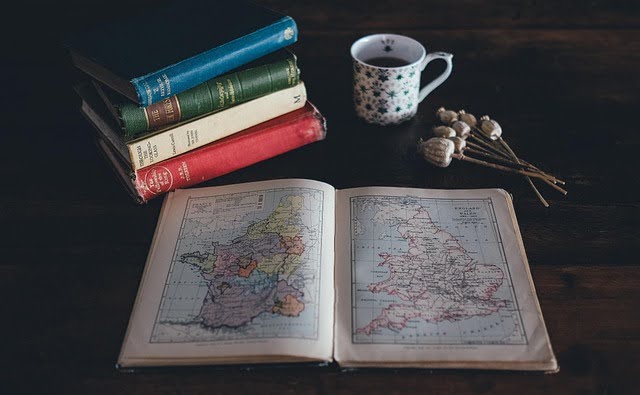
休憩や食後、気分転換など、普段から親しんでいるコーヒーには、古くからの歴史があります。コーヒーと人々との関わりや、コーヒーが文化として根づくまでの歴史についてご紹介しましょう。
コーヒーの歴史~10世紀頃まで

まずは、10世紀頃までのコーヒーに関する情報や伝説などについて見ていきましょう。
コーヒーの始まりはアフリカから
コーヒーの原産地は、アフリカのエチオピアといわれています。エチオピアはアフリカの北東部に位置する内陸の国で、現在もコーヒーの主要な生産国として知られています。コーヒー豆ができるコーヒーノキがいつ発見されたのか正確な年代はわかっていませんが、10世紀頃までにはエチオピアからイエメンへとコーヒーが伝えられたといわれています。
◇ 関連記事:「 エチオピアコーヒーとは?歴史や特徴、おすすめの飲み方を紹介 」
コーヒーにまつわる伝説
エチオピアとアラビアに伝わる2つの伝説をご紹介します。
・エチオピアのヤギ飼いカルディの伝説
9世紀頃、ヤギ飼いのカルディという少年は、ヤギが赤い実を食べて踊っているのを見つけ、好奇心から自分も実を食べてみたところ元気になり、ヤギと一緒に踊り出したといわれています。
その後カルディから赤い実の話を聞いたある僧侶が修道院へ実を持ち帰り、砕いてお湯に溶かして飲んでみたところ、活力と集中力が湧いてきたため、他の僧侶へもすすめ「神の贈り物」として広まっていったとされています。
・アラビアのイスラム教の聖者シークオマールの伝説
アラビアのイスラム教聖者であるシークオマールは、ある日領主の誤解から住んでいたイエメンのモカの町を追放されてイエメンのとある山へたどり着きました。そこで鳥が赤い実をついばんでいるのを見つけて自分も食べてみたところ、たちどころに空腹と疲労が癒され、活力が湧いてきたといわれています。
その後町に病気が蔓延して困っていたモカの人々の窮状を知ったシークオマールは、赤い実を煮出したものを分け与えました。すると、病状が回復し、シークオマールは「モカの守護聖人」として称えられたといわれています。モカは後にコーヒー豆の重要な輸出港として栄え、現在も古くからの生産地として人気があります。
コーヒーの歴史~13世紀頃まで

13世紀頃までのコーヒーに関する歴史を紹介します。
アラビアで薬として用いられる
13世紀頃のアラビアでは、イスラムの医学者や哲学者がコーヒーの効能や飲み方などを記したとされています。消化促進や利尿作用、身体の強化など、当時は医薬品のような位置づけで研究されていたのではないかといわれています。
飲料としてのコーヒー「カフワ」
コーヒー豆を煎って煮出すという方法は、13世紀後半頃にイエメンで広まったといわれています。
コーヒーは当時アラビア語で「カフワ」と呼ばれるようになったとされており、カフワには「眠りを防ぐもの」や「ワイン(のような香り高いお酒)」という意味があるほか「カッファ(コーヒーの産地)」という意味で呼ばれていたなど諸説あるようです。
コーヒーの歴史~16世紀頃まで
16世紀頃までのコーヒーに関する歴史をご紹介していきます。
コーヒーノキの栽培が始まる
15世紀に入ると、イエメンの聖者がコーヒーの産地であるエチオピアを訪問し、コーヒーの効能などに関する知識を得てイエメン全土へコーヒーを広め、イエメンでコーヒーノキの栽培が始まります。
お酒が禁じられているイスラム圏では、お酒に替わるものとしてコーヒーが大人気となったといわれています。
中東地域へと広がるコーヒー
16世紀になるとイエメンだけでなく、セイロンやエジプト、トルコへもコーヒーが広がっていきます。
オスマン帝国では、コーヒー豆を焙煎して細かく挽き、抽出する飲み方が生まれます。
世界最初のコーヒーハウス「カーヴェハーネ」がイスタンブールに誕生し、中東地域を旅していたドイツ人医師レオンハルト・ラウヴォルフが著した「旅行記」にも、コーヒーの記述が見られるようになっています。この旅行記におけるコーヒーの記述は、コーヒーに関する世界最古のものであるといわれています。
コーヒーの歴史~18世紀頃まで
18世紀頃までのコーヒーに関する歴史をご紹介します。エチオピアからイエメン、中東全土へと広がったコーヒーは、ヨーロッパへも伝わっていきます。
ヨーロッパへと伝わるコーヒー
17世紀に入ると、コーヒーがキリスト教圏であるヨーロッパへも伝わるようになります。
セイロンからジャワ島、スマトラなどへコーヒーが移植され、イタリアやフランス、ドイツ、イギリスなどでコーヒーハウス文化が花開くなど、ヨーロッパでもコーヒーは人気となっていきます。
ヨーロッパからアメリカへ
18世紀にジャワ島からアムステルダム植物園へ持ち込まれたコーヒーノキの種子から、コーヒーはアフリカ、中東からヨーロッパを超えて世界へと広く伝わっていくこととなります。
アフリカ西海岸や現在のコーヒー一大生産地である南米へと持ち込まれたのもこの頃であるといわれています。
コーヒーの歴史~現代へ
ここでは、現代までのコーヒーに関する歴史や、日本におけるコーヒーの歴史について見ていきましょう。
日本におけるコーヒーの歴史
日本へコーヒーが紹介されたのは19世紀頃、医師シーボルトによって伝わったといわれています。
1858年には日米修好通商条約によって正式にコーヒー豆の輸入が認められ、日本国内で急速にコーヒーが広まっていくこととなります。
明治時代後半から大正時代にかけてカフェも続々とオープンします。インスタントコーヒーが発明されたのも、日本人科学者の手によってであるといわれています。
戦後の日本におけるコーヒー文化
昭和初期を経て、戦後の日本におけるコーヒー文化、キーコーヒーの歩みについてもご紹介します。
1937年の第二次世界大戦中は、生豆の輸入禁止や食糧・物資にも事欠く時代となっており、コーヒーはまだ上流階級の人向けの飲み物でしたが、たんぽぽの根などを使った「代用コーヒー」を楽しむ人もいるなど、コーヒー文化は広く根づくものでした。
戦後1950年代になってからはコーヒーの輸入が再開し、港でたくさんの積荷を見て嬉しさと喜びに包まれる人も多かったといわれています。

1953年には株式会社木村コーヒー店(現キーコーヒー株式会社)が業界の先鞭をつけて ブルーマウンテン を輸入、 キリマンジャロ も取扱いがスタートします。

当時コーヒー1杯は30~50円ほどで、現在の価格にすると1,000円ほどであったようです。キーコーヒーのコーヒー教室ができたのも1955年のことです。喫茶店のプロでさえ把握しきれていなかったコーヒーの正しい知識・技術を広めるために、キーコーヒー本社に「コーヒー教室」を開校します。その後は百貨店をはじめ学校、店頭などでも開催をスタートしていきました。
1960年代に入ると、戦後の復興と共に個人経営の喫茶店は最盛期を迎えます。モーニングサービスの流行やランチ、食事が出来る喫茶店なども登場すると共にコーヒーの消費量も増え、この頃日本のコーヒー生豆輸入量は世界第12位になりました。

高度経済成長期を経て、80年代にはファミリーレストランやファストフードも急速に出店拡大し、コーヒーが楽しめる場所も増えていきます。家庭用のコーヒーメーカーも普及し始め、手軽に楽しめる飲み物として国内へ浸透していきます。
1990年代に入ると、シアトル系カフェブームが台頭し、深煎りのコーヒーやブレンドコーヒー、カフェラテなどミルクアレンジしたコーヒードリンクが人気となります。
2000年代以降はコーヒーニーズが多様化し、深煎りやブレンドだけでなく、浅煎りのシングルオリジンの人気も高まっていきます。
より高品質なスペシャルティコーヒーを1杯ずつ丁寧にいれるブームが始まったのもこの頃です。
自宅でも楽しめるコーヒー文化と今後の取り組み
現代では、シアトルスタイルや純喫茶など、さまざまなカフェでコーヒーが楽しめる一方で、自宅で本格的なコーヒーを楽しむことも可能になっています。
「自宅で自分の手で抽出する」「コンビニやファストフードで手軽に」「コーヒー農園から豆選びまでこだわって」など、コーヒーの楽しみ方も多様化しています。
コーヒーを楽しむ需要が拡大する一方で、地球温暖化によってコーヒー農園が半減するといわれている「2050年問題」も取り沙汰されており、 持続的なコーヒー生産に向けた対策が急務となっています。
コーヒーの歴史と共に、コーヒーの品質やコーヒー農園を守るための取り組みなどについても引き続き注目していきましょう。
◇ 関連記事:「
コーヒーのサステナビリティを考える
」
歴史を知ってコーヒーをもっと楽しもう
コーヒーにはおよそ1,000年に渡る長い歴史があり、その味わいや効能などから世界中の人々に愛されてきました。コーヒーの歴史を知ることで、コーヒーの魅力や当時の人々の開発努力などに思いを馳せて楽しみつつ、未来のコーヒーを守るために自分自身ができる取り組みについても考えてみましょう。